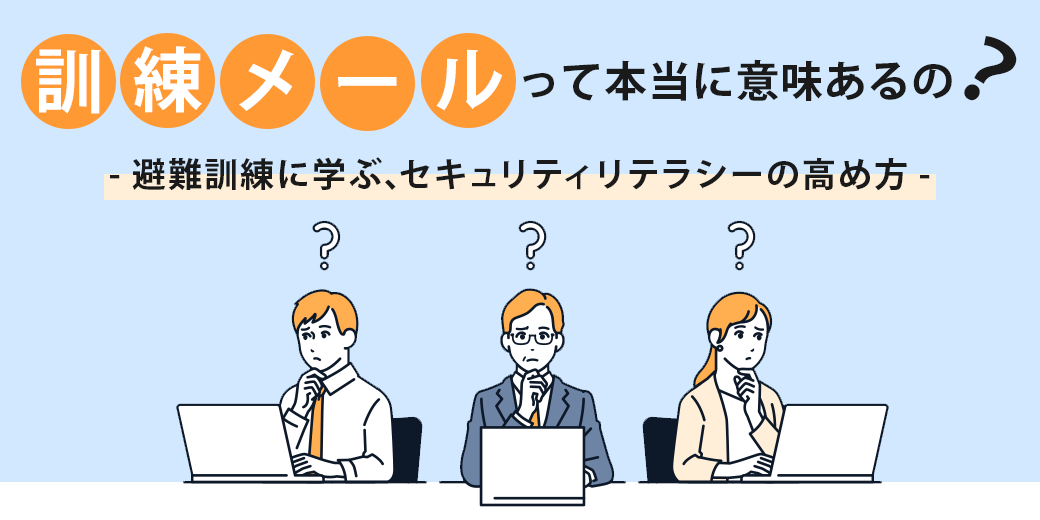
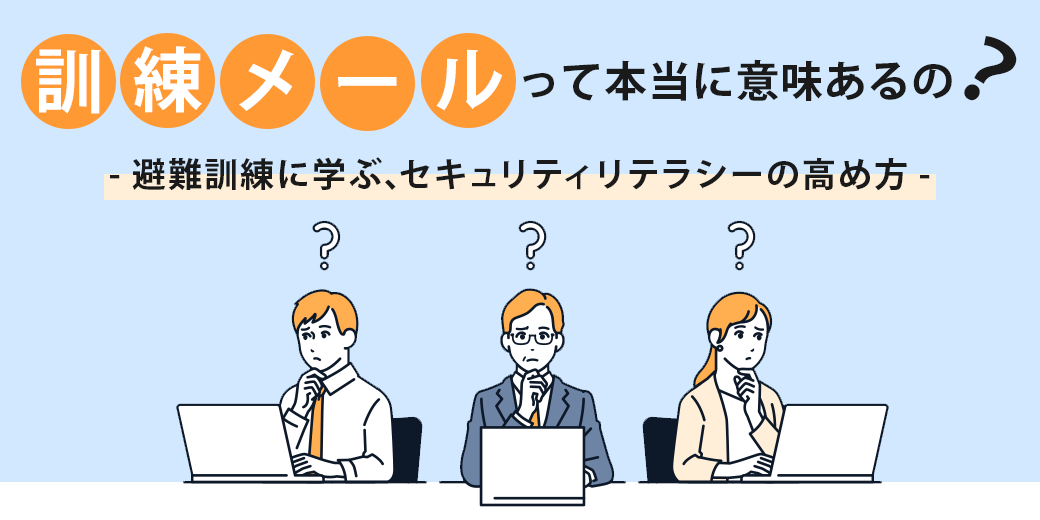
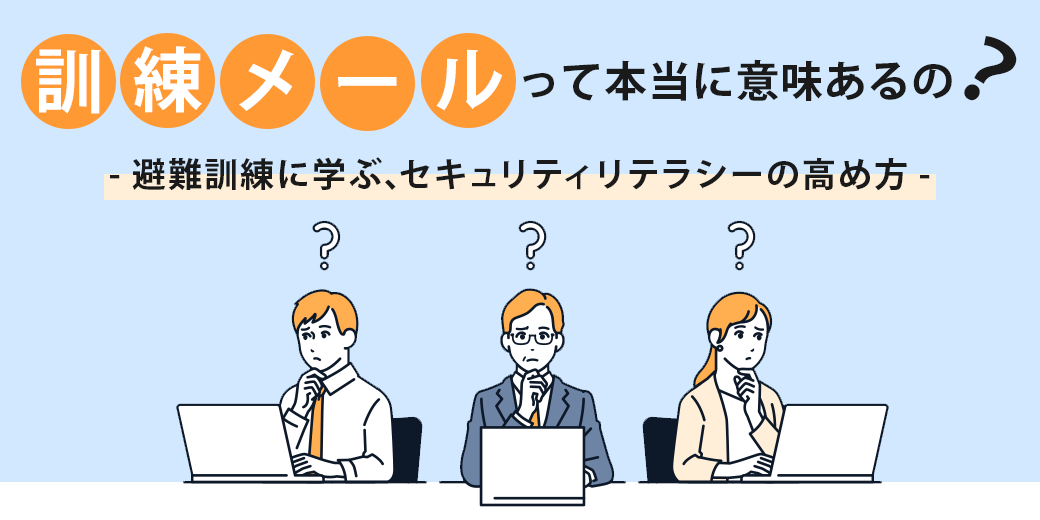
こんにちは。株式会社クオリティアです。
「また訓練メールか…」と流してしまった経験はありませんか? 標的型攻撃メール対策として多くの企業で行われている訓練メールですが、形骸化しやすく「本当に効果があるの?」という疑問も少なくありません。しかし、その存在意義は、私たちが子どもの頃に経験した 避難訓練によく似ています。一見意味がなさそうに見えても、いざというときに体が自然と動くのは、日常の訓練の積み重ねがあるから。
本記事では、避難訓練を例にしながら、訓練メールがなぜ組織にとって欠かせないのか、どのようにすれば効果を発揮するのかを解説します。
「フィッシング訓練メールが届いたけれど、特に何もせず削除して終わり」
「毎回やっているけど、正直なところ意味があるのか疑問」
多くの企業で定期的に実施されている訓練メール。それはセキュリティ担当者にとっては重要な施策ですが、一般社員にとっては「社内イベントの一つ」くらいの感覚で受け流されがちです。
実際に訓練後のアンケートでよく出てくる声としては、
「訓練だとわかっていたので深く考えなかった」
「業務が忙しく、まともに読まずに削除してしまった」
「毎回やっているが、何を学べばいいのかよくわからない」
といったものもあります。
このように、せっかくの訓練が効果を十分に発揮していないケースは少なくありません。
では、訓練メールは本当に意味がないのでしょうか?
ここで一度、子どもの頃を思い出してみてください。小学校や中学校で行われた避難訓練。
地震を想定して机の下に潜ったり、火災を想定して校庭に避難したりしましたよね。
正直なところ、当時は「本当にこんなことが役に立つの?」「授業がつぶれるからちょっと嬉しい」くらいの感覚だった方も多いと思います。しかし、実際に地震や火災が発生したとき、私たちは訓練で体に染み込んだ行動を自然と取ることができました。
地震が起きたらすぐ机の下に隠れる、火災警報が鳴ったら出口に向かうなど、頭で考える前に体が動いた、という経験をした方もいるでしょう。この「意味がわからなかったけど繰り返した経験」が、いざというときに命を守る行動に直結していたのです。
災害時に冷静に動けるかどうかは、その場の知識よりも 「日常的な繰り返し」 に左右されます。訓練を通じて体に覚え込ませておくからこそ、パニックの中でも正しい行動がとれるようになります。
では、現代の私たちを脅かす“災害”は何でしょうか。もちろん地震や火災への備えは依然として重要ですが、サイバー攻撃もまた大きな脅威になっています。本物そっくりに作られた銀行や通販サイトのフィッシングメール、取引先を装い請求書や契約書を添付する標的型攻撃メール、経営層を装って送金を指示するビジネスメール詐欺(BEC)など。これらの攻撃は年々巧妙化しており、たとえセキュリティリテラシーがある社員でも騙されてしまうケースが報告されています。
そして、一度被害を被ってしまうと、その影響は甚大です。顧客情報や機密情報の漏えい、システム障害による業務停止、社会的信用の失墜、多額の損害賠償や罰金など。つまり、サイバー攻撃はもはや「見えない災害」なのです。その災害に私たちはどこまで備えられているでしょうか?
ここで訓練メールの役割を考えてみましょう。訓練メールは、単に「騙されるかどうか」をテストするためのものではありません。もっと重要なのは “気づき” と “行動の習慣化” です。
✓気づきの強化
実際の業務環境と同じ状況でメールを受け取ることで、「あれ、ちょっと怪しいな」と感じる感覚を養うことができます。実際に送られてくるメールを体験するからこそ、座学よりもリアルに危険を想像できるのです。
✓行動の習慣化
さらに重要なのは、気づいた後の行動です。怪しいと思ったら削除するのではなく、上司やシステム部門に報告する、同僚に共有して注意を促す、自らの行動が組織全体のセキュリティにつながると理解する、このような一連の流れを訓練を通じて繰り返すことで、「疑う →報告する →共有する」という行動習慣が自然と身につきます。
訓練メールは、このような文化を育てるためのきっかけなのです。
では、訓練メールは実際にどんな成果をもたらしているのでしょうか。IPA(情報処理推進機構)が過去に公表した調査によると、フィッシング訓練を数ヶ月継続して行った企業では、社員の報告率が大幅に向上しました。
さらに、国内外のメール訓練を継続した企業の事例では、
•訓練を重ねることで「不審メールを削除して終わり」から「すぐに報告する」へ行動が変わった
•実際の攻撃メールをいち早く社員が報告し、被害拡大を防げた社員が「自分もセキュリティ対策の一部だ」と意識を持つようになった
といった成果が確認されています。このように、訓練メールは単なるチェックリストではなく、組織のセキュリティ文化を根付かせるきっかけになりうるのです。
ただし、訓練を一度や二度行っただけでは効果は限定的です。避難訓練と同じで、繰り返し行い、習慣に落とし込む必要があります。
その際のポイントは
✓パターンを変えて送る(件名や送信者を巧妙にする)
✓定期的に社員の声をフィードバックし、改善する
✓成果を数値で可視化し、社員に共有する
✓部署ごとや個人ごとに工夫を凝らした訓練を設計する
などの工夫することです。単調な訓練は「またか」と受け流されてしまいます。形骸化しないように工夫のある訓練を繰り返し行うことが重要です。
最後にもう一度、避難訓練との共通点を思い出してください。避難訓練は「意味がある」と感じるのは、実際に災害が起きた後です。しかし、そのときに初めて価値を理解しても手遅れです。
訓練メールも同様です。何も起きていないときに繰り返し行い、自然な行動を身につけておくことが、非常時に組織を守る力となります。
弊社の標的型攻撃メール訓練サービス「dmt」は、月額150円(税別)/1メールアドレスあたりで回数無制限の繰り返し訓練を可能にし、即時フィードバックの仕組みを持ち、300種類以上のテンプレートで多様なパターンによる訓練を実施できます。
dmtについてはこちら
詳細については、以下より遠慮なくお問い合わせください。
資料請求はこちらお問い合わせはこちら
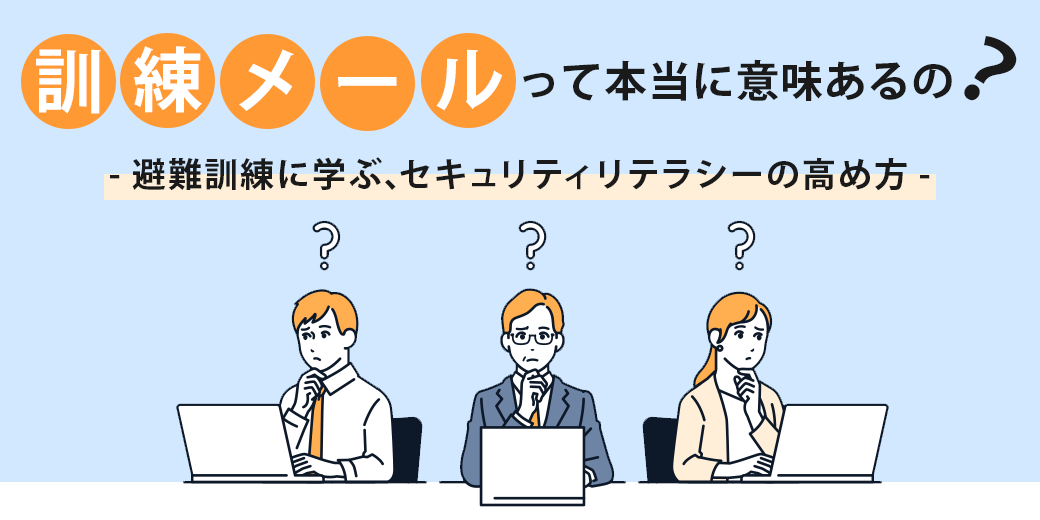
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
メールソリューションに関する
ご質問・資料請求などございましたら
お気軽にお問い合わせください。
お電話からのお問い合わせ
03-5623-2530フォームからのお問い合わせ
資料請求ダウンロードお見積り依頼・ご質問・ご相談はこちらから新規のお客様・パートナー様既存のお客様・パートナー様